健康経営とは?従業員・企業・社会を繋ぐ架け橋
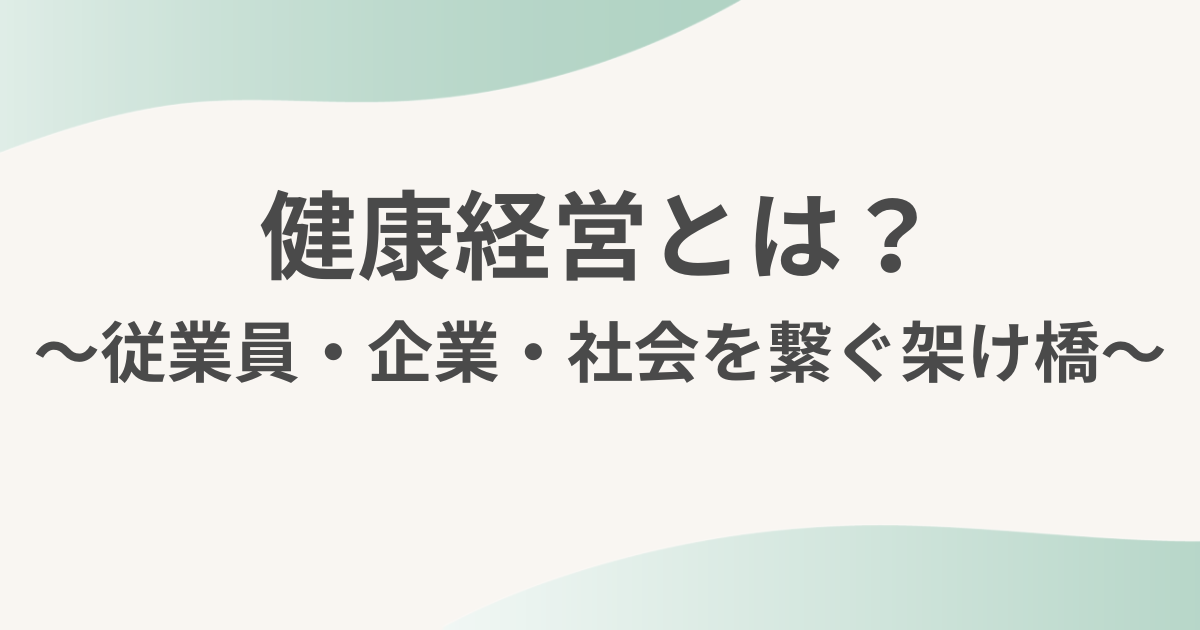
健康経営とは
健康経営とは、社員の健康を守ることを“コスト”ではなく“投資”と考え、企業の成長につなげる取り組みです。
ただの福利厚生ではなく、企業が従業員の心身の健康を守ることを計画的及び戦略的に行うことで、結果として企業の成長に繋がります。
「健康経営」とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。企業理念に基づき、従業員等への健康投資を行うことは、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や株価向上につながると期待されます。
健康経営は、日本再興戦略、未来投資戦略に位置づけられた「国民の健康寿命の延伸」に関する取り組みの一つです。
こんなことありませんか?
「最近、社員が就業時間中にぼんやりしていることが増えた。」
「慢性的な身体の痛みや、肩こりで仕事の手が止まる。突然のぎっくり腰で仕事どころではなくなる。」
「身体や心のストレスを抱えていて、社員同士の関係がギクシャクしている。」
こういった、“気になるけどなんとかなる程度の不調”が実は職場全体の生産性を下げています。
身体の不調が精神的に影響を与えることで、職場環境雰囲気に大きく影響します。
理学療法士として、働き、メンタルヘルスに関するリハビリテーションにも力を入れている立場から見ても、身体の不調というものは心に多大な影響を与えることを実感しています。
痛みや不調が常に心にストレスを与え、無意識のうちにゆとりがなくなっていきます。そして、誰かに優しく接することも難しくなり、ギスギスしていきます。
例えば、自分がお腹が痛くて仕方ない時に人助けをすることができるでしょうか?多くの方が難しいと思います。
これらの社員1人1人の健康管理を“個人の問題”として片付けるのではなく、“経営課題”として捉える考え方が、いま注目されている健康経営です。」
健康経営が注目される理由
健康経営が注目される背景には、日本全体の社会構造の変化があります。
まず、生産年齢人口(15〜64歳)は長期的に減少し続け、一方で65歳以上の人口は2050年頃には全体の約40%に達すると予測されています。
企業は高齢者も活躍できる職場環境を整えることが必須となり、その基盤として健康経営が欠かせません。
さらに、中小企業の経営者の6割以上が「人手不足」を実感しており、採用の難しさが続く中で、既存社員の定着率を高める取り組みが重要となっています。
また、国民医療費は高齢化や医療の高度化により増え続けており、企業が負担する健康保険料の上昇という形で経営を圧迫します。
従業員の健康維持は、企業の財政的負担を軽減する意味でも大きな効果を持っています。
上記の人口や医療費の問題だけではありません。
同時に、職場の現場も変化しています。未来に希望が溢れていた行動経済成長期に活躍された方々と、日本の将来を憂いながらも、物価高と上がらない賃金の中で、なんとか将来のために生きていこうとしている若い世代。
こういった世代間の価値観の違いによるギャップはそう簡単に埋めることはできませんし、お互いのことを理解し合うことすら難しい状態です。
価値観の不一致などによって、心理的安全性が低下している中で、現代は転職が一般化しています。
そんな、時代背景の中で、「ここで働き続けたい」と思ってもらえる環境づくりは欠かせません。
健康経営は三方良し
健康経営は従業員の健康を守るための経営手法になりますが、従業員にしかメリットがないという訳ではありません。
むしろ、普通の福利厚生以上に企業にも地方自治体や国にもメリットがあるものとなっています。
従業員にもメリットがあり、企業にもメリットがあり、地方自治体や国にもメリットがある。
うまく実施することで、誰も損をせず、みんなの幸せに繋がる仕組みとなります。
1.従業員側のメリット
・心身のコンディション改善:肩こり、腰痛、睡眠障害、ストレスなど、日常の不調が軽減されることで、快適に働けるようになります。
・安心できる職場環境:企業トップが健康投資に力を入れてくれることで、心理的安全性生まれ、「自分のことを大切にしてくれている」という信頼感に繋がります。
・ライフスタイル全体への波及:職場での健康行動が、家庭や日常生活に広がり、長期的な健康寿命の延伸や働くモチベーションアップに繋がります。
2.企業側のメリット
・生産性向上:従業員の体調不良やメンタル不調による「プレゼンティーズム(出勤しているが生産性が低い状態)」や「アブセンティーズム(欠勤)」を減らすことで、生産性が向上し、企業への利益に繋がります。
・人材定着と採用力向上:健康的に働ける職場環境は「ここで働きたい」という動機付けにつながり、離職率の低下や優秀な人材の確保に効果を発揮します。
・医療費・社会保険料負担の抑制:社員の健康状態が改善されれば、医療費の増大や企業負担の上昇を抑えることに繋がります。
・企業価値の向上:健康経営優良法人の認定などを通じて、取引先や金融機関、投資家からの信頼が高まり、ブランド力が向上します。
3.地方自治体と国のメリット
・地域の活力向上:地域住民の健康寿命が延びることで地域の活力が保たれることに繋がります。
・地域の雇用促進:健康経営に取り組む企業が集まることで、地域の雇用・定住促進に繋がります。
・地域および国民医療費の抑制:国民医療費の増加を抑制することができ、財政負担の軽減に繋がります。
・生産年齢人口の延長:健康寿命延伸によって労働力人口を確保することができるようになります。
まとめ
・健康経営とは、単なる福利厚生ではなく 「社員の健康を守ることを投資と捉え、企業の成長につなげる戦略」
・日本の社会構造の変化や、働く世代の価値観の違いが顕著になる現代において、健康経営は企業存続のための必須要素となっている
・健康経営は「従業員」「企業」「社会・国」の三方すべてにメリットをもたらし、組織の活性化・人材の定着・地域社会の持続可能性に直結する
・健康経営は 企業の未来を守るための“成長戦略” である
振り返り
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
この記事から、健康経営に繋がる気づきや、健康経営を取り組むためのヒントが見つかっていれば嬉しく思います。
そして、最後まで読んでくださった企業様にはもう一歩踏み込んで考えていただきたいと思います。
・あなたの職場には、どんな「不調」が多く見られますか?
・社員の健康が改善されたら、どんな雰囲気や成果が生まれると思いますか?
・「ここで働きたい」と思ってもらうために、まずできる一歩は何でしょうか?
・貴社にとって「健康経営」が単なるコストでなく“投資”になるのは、どんな場面でしょうか?
実践できる取り組み
上記を考えられる経営者様や管理職の方は、従業員の健康や企業自体の健康に意識を持って取り組まれている方かと思います。
先ほど考えた問いに対して、何か一つ実践ををしていただくと、本当の健康経営に近づいていくのではないかと思っています。
・健康経営の事例を調べ、自社に合う取り組みを一つ試してみる
・一日の中で五分間のストレッチ時間をつくる
・まずは社員に「最近、体調や働き方で気になることは?」と聞いてみる
・月に一度、短時間でも体を動かすリフレッシュタイムを取り入れる
小さな一歩でも、踏み出すことが次に繋がり、従業員および企業の健康を守る活動になります。
ぜひ、小さな一歩から始めていただければと思います。
ZEN-Shinについて
ZEN-Shinでは、理学療法士の専門性を活かした
・セミナー型研修
・ワーク型研修
・職場環境改善
・健康経営導入サポート
を通じて、企業の「健康経営」を実践的に支援しています。
「まず何から始めたらいいのか」「従業員が喜ぶ取り組みにしたい」といったご相談も歓迎です。
御社の健康経営の第一歩を、サポートさせていただきますので、ぜひ一緒に歩んでいきましょう。
